結婚式のスタイルを決めるときに最初に悩むのが「和装にするか、ドレスにするか」である人も多いのではないでしょうか。
厳かで伝統ある神前式にも憧れるし、やっぱり純白のウェディングドレスを着る夢も捨てがたい。私もかなり悩みました。
そして、どちらも諦めたくない…そんな気持ちから、私は「神前式で白無垢を着て挙式、披露宴ではウェディングドレス」という方法を選びました。
今回は、そんな私の体験を、実際の流れや準備の工夫、そして感じたことを交えながらご紹介します。

私も憧れを詰め込んだ結婚式を挙げました!
白無垢とウェディングドレスどっちも着たい!
神前式でもウェディングドレスが着たい
私が神前式を選んだ理由はこちらの記事で書いています。
ざっくりまとめると
- 誓いのキスに抵抗がある
- 厳かな雰囲気で挙式がしたい
- 神社が好き
というような感じです。この条件にぴったりなのは、神前式なんですよね。
でも、同時に「ウェディングドレスを着ること」もひとつの夢でした。真っ白なドレスも花嫁の象徴、小さな頃から憧れです。
両親からも「娘のウェディングドレス姿が見たい」と折りに触れて言われてました。
でもやっぱり神前式が第1条件。ドレスは諦めようと思いつつ調べてみると「神前式で挙式、披露宴でドレス」というスタイルもできると知って、「これだ!」と。
神前式の厳かさも、ドレスの華やかさも、どちらも体験したい私にはぴったりの形でした。
白無垢からウェディングドレスにお色直し
まず、神前式では綿帽子+白無垢の正統派スタイル。披露宴では綿帽子を外して入場しました。
披露宴でガラリと雰囲気を変えたい方は、この時に色打掛にするのもおすすめ。白無垢→色打ち掛けの場合、土台はそのままで1番上を掛け替えるだけなので、15分ほどで可能だと教えてもらいました。

私が色打ち掛けを選ばなかったのは単に予算の都合…
披露宴の前半は白無垢で過ごして中座、そこからウェディングドレスへとお色直し。同じ「白」でも、和装の白無垢とはまったく違う雰囲気で、家族や友人にも好評でした。
お色直し後に各テーブルを回って写真撮影をしたのですが、ドレスの方が動きやすいのでその点も良かったです。
髪型はどうする?
綿帽子の中は洋髪のまとめ髪にして、披露宴入場のときは綿帽子を外すだけにしていました。
綿帽子の中は周りから見えないので、外すと結構印象が変わります。ただし、神前式は洋髪NGとしているところもあるので、注意が必要です。
ウェディングドレスにお色直ししたときはハーフアップスタイルに変えました。
お色直しの意味と考え方
お色直しの意味って?
もともとは、花嫁が嫁ぎ先の家に合わせて衣装を変える儀式が始まりです。
昔の日本では、結婚とは「新しい家に入る」こと。
白無垢=「どんな色にも染まっていない真っ白な自分」を表していて、神前式のときは白無垢を着て「これからあなたの家の色に染まります」という意味を込めていました。
その後、披露宴などの場では色打掛や振袖などに着替えて、「新しい家に馴染んだ」「家の一員として受け入れられた」という意味を表していたんです。
つまり、
お色直し=“嫁入りのけじめ”や“新しい人生への変化”を象徴する儀式
なんです。
白から白へのお色直しはNG?
お色直しの意味を考えると、白無垢からウエディングドレスという「白から白」へのお色直しはNGでは?と思う方もいるかと思います。
私も気になったので結婚式場のプランナーさんに確認したところ、
白無垢は「嫁ぎ先の家の色に染まります」という意味を持ち、ウェディングドレスは「純潔」や「新しい人生のスタート」の象徴です。
同じ“白”でも、込められた想いが違うんです。
だから、白から白へのお色直しは「二つの誓い」を表現できる、とても素敵な選択なんですよ。
と教えてもらいました。
現代においては
- ゲストに楽しんでもらう演出のひとつとして取り入れる
- 花嫁自身が「違う自分を表現したい」「せっかくの機会だから色々着たい」という想いから選ぶ
など、“変化を楽しむ”という意味も強くなっていますので、あまり気にしすぎなくても良いと思います。
まとめ:白無垢とウェディングドレスは両方着てOK
神前式での厳かな空気と、披露宴での華やかな雰囲気。どちらも私にとって、かけがえのない大切な時間でした。
白無垢で誓いを立てた瞬間は、心が清められるような静かな気持ち、ウェディングドレスに着替えたときは、新しい自分として一歩を踏み出すようなわくわく感がありました。
神前式の夢とウェディングドレスへの憧れ、どちらも大切にしたことで「結婚式って本当に自由でいいんだ」と実感しました。
「神前式に憧れるけれど、ドレスも着たい」と悩んでいる方へ。どちらかを諦める必要はありません。工夫次第で、どちらの夢も一日に叶えることができます。
自分らしいスタイルを大切にすれば、その日がきっと一生の思い出になります。白無垢もウェディングドレスも、すべてが“あなたらしさ”を映す一着です。
そんな心に残る一日を、ぜひ楽しんでくださいね。
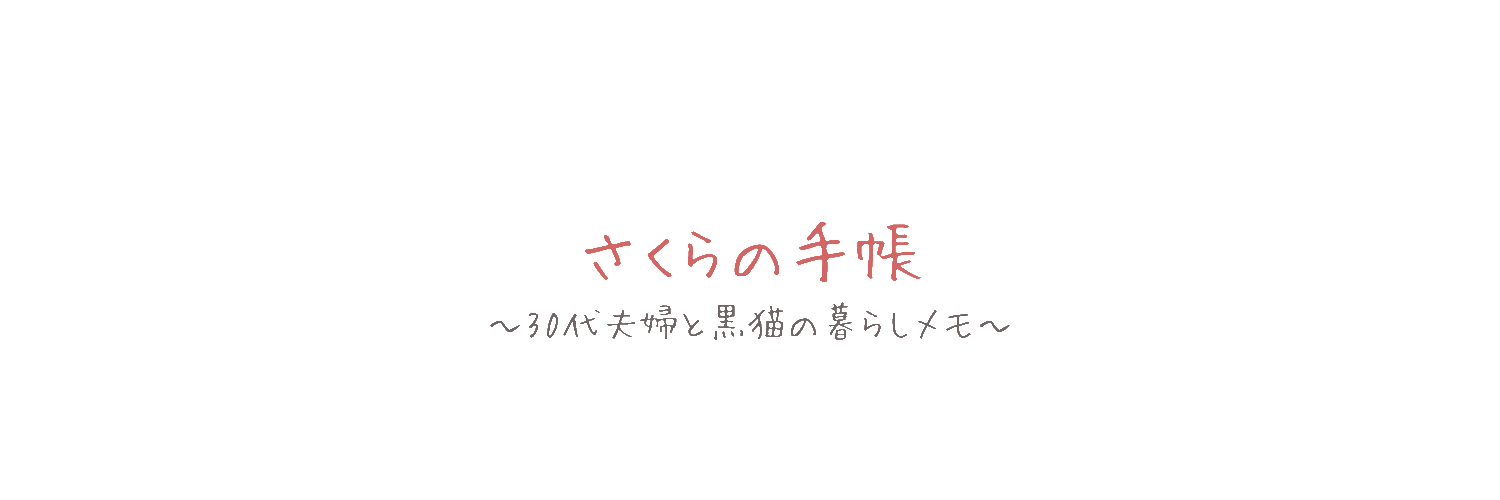
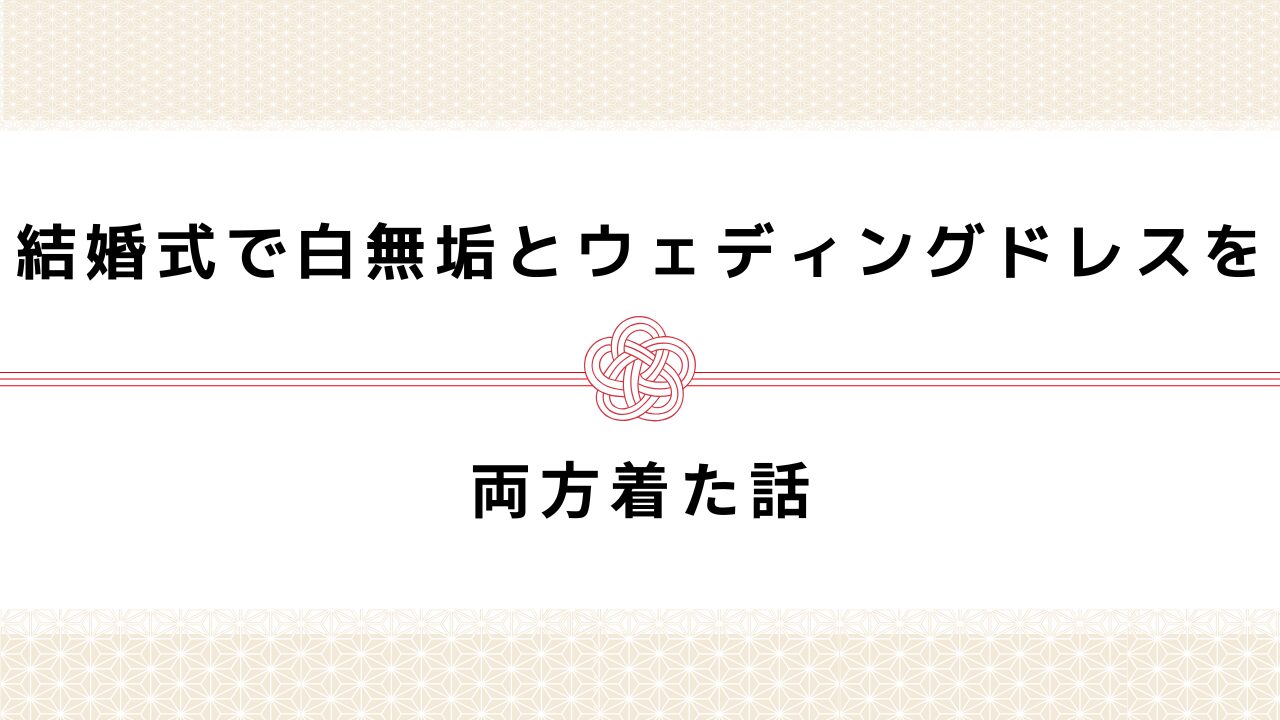
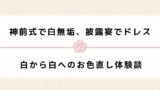
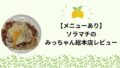

コメント